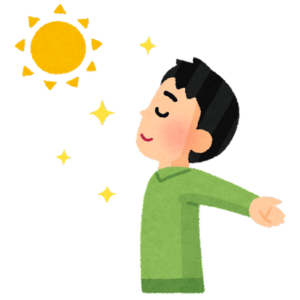気の乱れは、心の乱れ!東洋医学からみる鬱(うつ)症状

東洋医学からみる3つの鬱(うつ)タイプ
10月の凜鍼灸治療院ブログでは「季節性うつ病」についてお伝えしています。
秋から冬になると気分が落ち込んだり、日中でも眠気がでたり、仕事に集中できなくなるなどの症状がでやすくなります。
これを「季節性うつ病(季節性感情障害)」と呼びます。
現代医学では、秋から冬にかけ日照時間が短くなることで、幸せホルモンであるセロトニンの分泌量が減り、体内時計のバランスをつかさどっているメラトニンの分泌の乱れにより抑うつ症状が引き起こされると考えられています。
さまざまな精神疾患は現代医薬で治療をしないと重症化する恐れがあるので、ひとりで抱えこまず専門の医療機関に早めに相談に行きましょう。
では、東洋医学では日常生活に支障をきたすほどではない軽いうつ症状をどのように捉えているのでしょうか。
東洋医学では、軽度のうつ症状の原因は「気の異常」と考えます。
東洋医学で考えるうつ症状の代表的な3つのタイプをみていきましょう。
| 鬱タイプ | 症状 | 原因 |
| 気滞(きたい)タイプ | 漠然とした不安感、ノドの異物感 | 気の巡りが滞っている状態 |
| 肝実脾虚(かんじつひきょ)タイプ | イライラ、筋肉の痙攣、食欲低下 | 肝に気が鬱積し熱を帯び、脾(消化機能)が低下した状態 |
| 気虚(ききょ)タイプ | やる気が起こらない、全身の倦怠感 | 気が消耗(エネルギー不足)している状態 |
東洋医学で考えられている生命活動のエネルギーである「気」は巡ることでバランスをとっています。
しかし、気の巡りが悪くなって気が滞った状態になったり、肝(臓器)に気が鬱積したり、気が消耗して不足してしまうと不安感やイライラ、倦怠感などの症状を引き起こしてしまいます。
東洋医学で考える「気の異常」による心の不調(うつ症状)も、長期間続く場合は我慢せず専門医に診てもらいましょうね。
次回は「季節性うつ病の予防ポイント」についてお伝えします。
本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
ご予約受付〈30日前〜30分前まで〉
ご予約前にお読み下さい。→